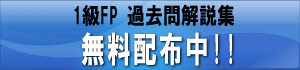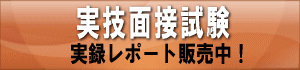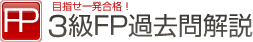問22 2013年9月基礎
問22 問題文
デリバティブの活用によるリスクヘッジに関する次の記述のうち,最も適切なものはどれか。なお,取引の主体は各選択肢に記載されている経済主体とし,その取引の相手方について考慮する必要はない。
1) 外貨建て債券を発行する日本国内の事業会社が,将来の円安による償還負担増をヘッジするために,債券の償還日に合わせて外貨買い/円売りの為替予約を行った。
2) 短期金利に連動する変動金利で利息が計算されるシンジケート・ローンを借り入れている事業会社が,将来の金利上昇による利息負担増をヘッジするために,変動金利支払/固定金利受取りの金利スワップを行った。
3) 大量の固定利付国債を保有する銀行が,今後の金利上昇リスクをヘッジするために,長期国債先物を買建てした。
4) 継続的に米ドル建ての支払が発生する日本国内の輸入業者が,将来の円安による支払額の増加をヘッジするために,外貨固定金利支払/円固定金利受取りのクーポン・スワップを行った。
問22 解答・解説
デリバティブ取引に関する問題です。
1) は、適切。将来円安になると、円換算した場合の外貨建て債券の償還価格が上昇するため、発行会社の負担増となりますが、償還日に合わせてドル買い/円売りを行う為替予約を購入することで、円安リスクのヘッジを行うことが出来ます。
2) は、不適切。金利上昇時には、変動金利の支払い⇒支払増、固定金利受取り=そのまま、となるため、支払いが多くなってしまいます。
よって金利上昇のヘッジには、固定金利支払/変動金利受取の金利スワップが有効となります。
なお、シンジケートローンとは、顧客の資金調達ニーズに対し複数の金融機関でシンジケート団をつくり、同一条件で融資を行う資金調達手法です。
3) は、不適切。金利の上昇は債券価格の下落につながるため、長期国債先物の売りポジションを持っていれば、金利上昇時には債券価格の下落により長期国債先物も下落すると見込まれるため、金利上昇リスクに対するヘッジとして有効です。
4) は、不適切。ドルの固定金利支払い/円の固定金利受取りとなるクーポン・スワップでは、ドル高時に高くなったドルの金利を支払い、安くなった円の金利を受け取ることになってしまいます。
外貨払いにおける、外貨高/円安に対するヘッジには、円の固定金利支払い/外貨の固定金利受取りとなるクーポン・スワップが有効です。
関連・類似の過去問
この問題と似ている問題を検索してみよう!「検索」ボタンをクリック!
FP対策講座
<FP対策通信講座>
●LECのFP講座(キーワード検索欄で「1級」と検索) ⇒ FP(ファイナンシャル・プランナー)サイトはこちら
![]()
●1級FP技能士(学科試験対策)のWEB講座 ⇒ 1級FP技能士資格対策講座(資格対策ドットコム)
●通勤中に音声学習するなら ⇒ FP 通勤講座
![]()
●社労士・宅建・中小企業診断士等も受けるなら ⇒ 月額定額サービス【ウケホーダイ】
![]()
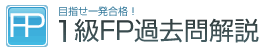
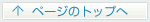
 ●無料アプリ版公開中。
●無料アプリ版公開中。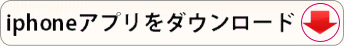
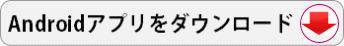
 ●広告無しの有料版。
●広告無しの有料版。