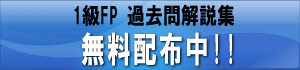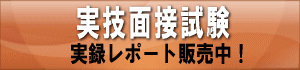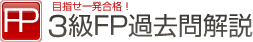問2 2015年1月基礎
問2 問題文
雇用保険の基本手当に関する次の記述のうち,最も適切なものはどれか。なお,いずれの場合も,所定の手続はなされているものとし,各選択肢で記載のある事項以外は考慮しないものとする。
1) Aさん(48歳)は,平成26年12月20日,「契約更新をする場合がある」とされていた雇用契約に基づき,契約更新を希望したにもかかわらず,2年間の労働契約期間満了により離職した。Aさんが待期期間満了後から受給することができる基本手当の日数は,最大で180日である。
2) 基本手当を受給しながら求職活動をしていたBさん(32歳)は,平成26年6月1日に再就職し,再就職手当を受給した。しかし,会社の業務になじめず,平成26年11月30日に自己都合退職した。この場合,Bさんが待期期間に加え,3カ月間の給付制限経過後に受給することができる基本手当の日数は,最大で90日である。
3) Cさん(52歳)は,30年間勤務した会社が経営難から廃業に追い込まれ,平成26年12月末で解雇された。この場合,特定受給資格者に該当するCさんが受給することができる基本手当の日数は,最大で240日である。
4) 60歳で定年に達したDさんは,会社の継続雇用制度を希望せず,38年間勤務した会社を定年退職した。この場合,Dさんは3カ月間の給付制限経過後から最大で180日の基本手当を受給することができる。
問2 解答・解説
雇用保険に関する問題です。
1) は、適切。雇用保険の基本手当は、会社都合退職である倒産・解雇による離職(特定受給資格者)や雇止めによる離職(特定理由離職者)の場合は、7日間の待期期間後にすぐ支給開始されます。
また、基本手当の所定給付日数は、離職理由(倒産・解雇等の場合は多い)、年齢(中高年の方が多い)、算定基礎期間(被保険者期間が長いほど多い)等により異なります。
Aさんの場合、年齢48歳・算定基礎期間2年ですので、雇止めの場合の所定給付日数は180日です。
(特定理由離職者、45歳〜60歳未満、被保険者期間1年以上5年未満→180日給付)
2) は、不適切。基本手当の所定給付日数が3分の1以上残っている状態で安定した職業に就くと、一定の要件を満たした上で、再就職手当が支給されますが、再就職後、基本手当の受給期間内(離職の翌日から1年以内)に再度離職した場合には、当初の受給資格に基づいて基本手当の支給が再開されます。
この場合、前回給付制限を受けていれば再離職の際は給付制限無しとなり、逆に前回給付制限を受けなかったが今回は自己都合退職等であれば給付制限されます。また、受給できる基本手当の日数は、既に支給した日数分と、再就職手当相当の日数分が差し引かれます。
従って、再就職後に自己都合退職したBさんには3ヶ月の給付制限期間があるため、前回は会社都合退職であったと思われます。よって、特定受給資格者で30歳〜35歳未満の給付日数は最大240日(被保険者期間20年以上)であり、再離職後に受給する基本手当からは、既に受給した基本手当や再就職手当分を差し引くため、「最大で90日」には必ずしもなりません。
3) は、不適切。基本手当の所定給付日数は、離職理由(倒産・解雇等の場合は多い)、年齢(中高年の方が多い)、算定基礎期間(被保険者期間が長いほど多い)等により異なります。
Cさんの場合、年齢52歳・算定基礎期間30年ですので、解雇の場合の所定給付日数は330日です。
(特定受給資格者、45歳〜60歳未満、被保険者期間20年以上→330日給付)
4) は、不適切。Dさんは勤続38年のため、被保険者期間20年以上と考えられます。65歳未満で被保険者期間20年以上の一般受給資格者の場合、基本手当の給付日数は150日です。
関連・類似の過去問
この問題と似ている問題を検索してみよう!「検索」ボタンをクリック!
FP対策講座
<FP対策通信講座>
●LECのFP講座(キーワード検索欄で「1級」と検索) ⇒ FP(ファイナンシャル・プランナー)サイトはこちら
![]()
●1級FP技能士(学科試験対策)のWEB講座 ⇒ 1級FP技能士資格対策講座(資格対策ドットコム)
●通勤中に音声学習するなら ⇒ FP 通勤講座
![]()
●社労士・宅建・中小企業診断士等も受けるなら ⇒ 月額定額サービス【ウケホーダイ】
![]()
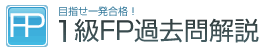
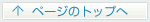
 ●無料アプリ版公開中。
●無料アプリ版公開中。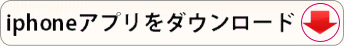
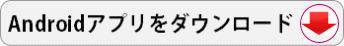
 ●広告無しの有料版。
●広告無しの有料版。