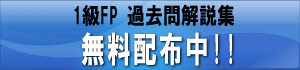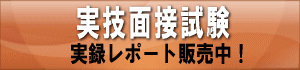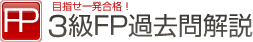問3 2018年9月基礎
問3 問題文
雇用保険の基本手当に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
1) 事業所の倒産により離職し、雇用保険の一般被保険者資格を喪失した者は、離職の日以前1年間に被保険者期間が通算して6カ月以上あれば、基本手当の受給対象者となる。
2) 基本手当の受給資格者が失業の認定を受けようとするときは、原則として、失業の認定日に、その者の住所または居所を管轄する公共職業安定所に出頭し、失業認定申告書等を提出して職業の紹介を求めなければならない。
3) 特定受給資格者以外の受給資格者(就職困難者を除く)の所定給付日数は、離職の日における年齢および算定基礎期間の長短に応じて、90日、120日、150日、180日のいずれかとなる。
4) 基本手当の受給期間が経過した場合、所定給付日数分の基本手当の支給を受けていないときであっても、その受給資格に基づく基本手当は支給されない。
問3 解答・解説
雇用保険に関する問題です。
1) は、適切。雇用保険の基本手当の受給資格は、離職の日以前2年間の被保険者期間が通算12ヵ月以上あることです(自主退職や契約期間の終了、定年退職等の場合(一般受給資格者))。
ただし、倒産・解雇による離職(特定受給資格者)や雇止めによる離職(特定理由離職者)の場合は、離職の日以前1年間の被保険者期間が通算6ヵ月以上となります。
2) は、適切。基本手当の受給資格者が基本手当を受給するためには、労働の意思・能力があっても就業できないという「失業の状態」にあるとして、ハローワークで失業認定を受ける必要があります。また、失業認定の際は、認定日に管轄のハローワークに直接出向いて失業認定申告書等を提出し、求職活動を行うことが必要です。
3) は、不適切。雇用保険の基本手当の所定給付日数は、離職理由(倒産・解雇等の場合は多い)、年齢(中高年の方が多い)、算定基礎期間(被保険者期間が長いほど多い)等により異なりますが、倒産・解雇で離職した特定受給資格者や、障害や社会的事情により就職が難しい就職困難者を除く一般受給資格者の場合、基本手当の給付日数は、算定基礎期間の長さに応じて90日、120日、150日の3段階に区分されています。
4) は、適切。基本手当の受給期間は、離職の日の翌日から起算して1年間ですが、「受給期間」=「手当を受給できる期間」ですので、受給期間を過ぎてしまうと、給付日数が残っていてももらえなくなるため、離職したらすぐにハローワークに行って手続きすることが重要なわけです。
よって正解は、3
関連・類似の過去問
この問題と似ている問題を検索してみよう!「検索」ボタンをクリック!
FP対策講座
<FP対策通信講座>
●LECのFP講座(キーワード検索欄で「1級」と検索) ⇒ FP(ファイナンシャル・プランナー)サイトはこちら
![]()
●1級FP技能士(学科試験対策)のWEB講座 ⇒ 1級FP技能士資格対策講座(資格対策ドットコム)
●通勤中に音声学習するなら ⇒ FP 通勤講座
![]()
●社労士・宅建・中小企業診断士等も受けるなら ⇒ 月額定額サービス【ウケホーダイ】
![]()
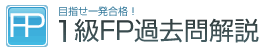
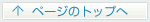
 ●無料アプリ版公開中。
●無料アプリ版公開中。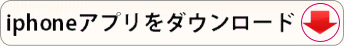
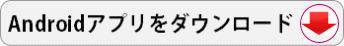
 ●広告無しの有料版。
●広告無しの有料版。