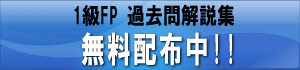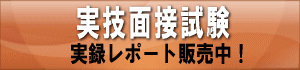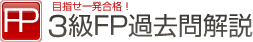問49 2020年9月基礎
問49 問題文
「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」(以下、「本特例」という)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、各選択肢において、ほかに必要とされる要件等はすべて満たしているものとする。
1) 被相続人の事業の用に供されていた宅地を被相続人の配偶者が相続により取得した場合、その配偶者が当該宅地を相続税の申告期限までに売却したとしても、当該宅地は特定事業用宅地等として本特例の適用を受けることができる。
2) 被相続人の居住の用に供されていた宅地を被相続人の親族でない者が遺贈により取得した場合、その者が相続開始の直前において被相続人と同居していたときは、当該宅地は特定居住用宅地等として本特例の適用を受けることができる。
3) 被相続人が発行済株式総数の全部を有する法人の事業の用に供されていた宅地を被相続人の親族が相続により取得した場合、その親族が相続開始の直前において当該法人の役員でなければ、当該宅地は特定同族会社事業用宅地等として本特例の適用を受けることはできない。
4) 被相続人の貸付の用に供されていた宅地を被相続人の親族が相続により取得した場合、その宅地が建物または構築物の敷地の用に供されているものでなければ、当該宅地は貸付事業用宅地等として本特例の適用を受けることはできない。
問49 解答・解説
小規模宅地の特例に関する問題です。
1) は、不適切。小規模宅地の特例は、基本的に相続税の申告期限まで居住用宅地は居住・所有継続し、事業用・貸付用宅地は事業や貸付を継続することが必要です。
2) は、不適切。 小規模宅地の特例は、民法上の親族(6親等内の血族、配偶者、および3親等内の姻族)が取得した場合に適用されるため、親族でない者は同居していたとしても対象外です。
(血族は血縁関係、姻族は配偶者の血縁関係)
3) は、不適切。特定同族会社事業用宅地等として小規模宅地の特例を受けるには、被相続人・親族・特殊関係人で50%超保有する法人の事業用(貸付事業を除く)の宅地であることと、相続や遺贈で宅地を取得した者が、被相続人の親族で、かつ相続税の申告期限までその法人の役員であり、その宅地を申告期限まで保有していることが必要です。相続税の申告期限の時点で役員に就任していればよいので、相続開始前に役員である必要はありません。
4) は、適切。小規模宅地の特例の対象は、「建物または構築物の敷地の用に供されているもの」であるため、駐車場の場合、土地の上に舗装などの何かしらの構築物があることが必要です(青空駐車場の土地については適用対象外)。
よって正解は、4
関連・類似の過去問
この問題と似ている問題を検索してみよう!「検索」ボタンをクリック!
FP対策講座
<FP対策通信講座>
●LECのFP講座(キーワード検索欄で「1級」と検索) ⇒ FP(ファイナンシャル・プランナー)サイトはこちら
![]()
●1級FP技能士(学科試験対策)のWEB講座 ⇒ 1級FP技能士資格対策講座(資格対策ドットコム)
●通勤中に音声学習するなら ⇒ FP 通勤講座
![]()
●社労士・宅建・中小企業診断士等も受けるなら ⇒ 月額定額サービス【ウケホーダイ】
![]()
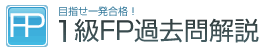
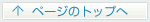
 ●無料アプリ版公開中。
●無料アプリ版公開中。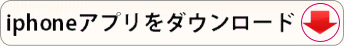
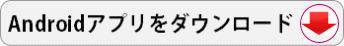
 ●広告無しの有料版。
●広告無しの有料版。