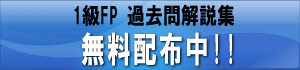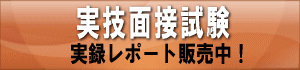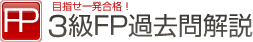問44 2023年9月基礎
問44 問題文
養子に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、本問においては、特別養子縁組以外の縁組による養子を普通養子といい、記載のない事項については考慮しないものとする。
1) 特別養子縁組は、特別養子適格の確認の審判と特別養子縁組の成立の審判により成立するが、特別養子適格の確認の審判の申立ては、児童相談所長が行わなければならず、養親となる者が申立てをすることはできない。
2) 特別養子の養親は、配偶者を有する者で、夫婦の一方が満25歳以上、かつ、夫婦のもう一方は満20歳以上でなければならないが、普通養子の養親は、満20歳以上であれば配偶者がいない者でもなることができる。
3) 普通養子は、養子縁組の日から養親の嫡出子としての身分を取得し、養親に対する相続権を有するとともに、実親との親族関係も継続するため、実親に対する相続権も有する。
4) 子を有する者を普通養子とした後、その普通養子が死亡した場合において、普通養子の死亡後に養親の相続が開始したときは、普通養子の子は、普通養子の相続権を代襲しない。
問44 解答・解説
普通養子・特別養子に関する問題です。
1) は、不適切。特別養子縁組は、実親の養育状況と同意の有無等を判断する特別養子適格の確認の審判と、養親子のマッチングを判断する特別養子縁組の成立の審判により成立しますが、特別養子適格の確認の審判は、児童相談所長または養親候補者が申し立てることになります(養親候補者が申し立てる場合は、成立の審判も同時に申し立てることが必要)。
2) は、適切。特別養子の養親は、配偶者がいて夫婦の一方が満25歳以上、かつ、夫婦のもう一方は満20歳以上であることが必要ですが、普通養子の養親は、満20歳以上であれば配偶者の有無は問われません。
3) は、適切。養子になると、養子縁組の日から養親の嫡出子(籍を入れた夫婦の子)としての身分と養親に対する相続権を取得しますが、特別養子縁組ではない、普通養子縁組の場合、養子と実の父母との親族関係は終了せず、養親だけでなく、実の父母が死亡したときにも相続人となることができます。
特別養子縁組とは、養子が戸籍上も実親との親子関係を断絶し、実子と同じ扱いとする縁組です。特別養子縁組が成立した場合、実の父母との親族関係は終了し、実の父母の相続人となりません。
4) は、適切。養子縁組成立前に生まれていた養子の子は、養親との間には法的な血縁関係が生じないため、養親の相続開始前に養子が死亡した場合、養親の相続が発生しても、養子縁組の成立前に生まれていた養子の子は、代襲相続できません。
なお、養子縁組の成立後に生まれた養子の子は、法的な血縁関係が生じるため、代襲相続可能です。
よって正解は、1
関連・類似の過去問
この問題と似ている問題を検索してみよう!「検索」ボタンをクリック!
FP対策講座
<FP対策通信講座>
●LECのFP講座(キーワード検索欄で「1級」と検索) ⇒ FP(ファイナンシャル・プランナー)サイトはこちら
![]()
●1級FP技能士(学科試験対策)のWEB講座 ⇒ 1級FP技能士資格対策講座(資格対策ドットコム)
●通勤中に音声学習するなら ⇒ FP 通勤講座
![]()
●社労士・宅建・中小企業診断士等も受けるなら ⇒ 月額定額サービス【ウケホーダイ】
![]()
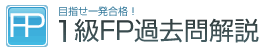
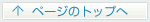
 ●無料アプリ版公開中。
●無料アプリ版公開中。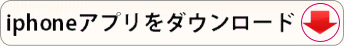
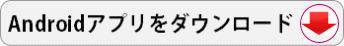
 ●広告無しの有料版。
●広告無しの有料版。